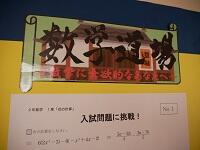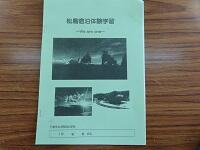西中ブログ
 「白湯」について
「白湯」について
今日の給食献立メニューは「ごはん・牛乳・鶏肉の塩唐揚げ・チンゲン菜のソテー・豆乳白湯スープ」です。今日は「白湯」についてのお話です。「白湯」という漢字には、「さゆ」「しらゆ」「はくとう」などの読み方があります。他にも「パイタン」とも読むそうです。「白湯(パイタン)鍋」や「白湯(パイタン)ラーメン」などは聞いたことがあると思います。では「白湯(パイタン)」とは、どのような意味なのでしょうか。中国語の由来によると、「湯(タン)」は中華料理ではスープを意味し、「白湯(パイタン)」は白濁したスープを指すそうです。また、一般には、鶏がらスープで味付けされた「鶏白湯」として知られているそうです。今日の給食は「豆乳白湯」ということで、栄養価の高い、豆乳で味付けされています。生徒の人気メニューでもあり、美味しそうに食べている様子でした。
 ミニ大根が発芽しました
ミニ大根が発芽しました
1年生が技術の授業で育てている「ミニ大根」が芽を出しました。これも1年生がよく観察し、適宜、水やりを行っていたからだと思います。休み時間の度に観察しに行く姿を嬉しく思います。
 修学旅行の結団式を行いました
修学旅行の結団式を行いました
6時間目に西中ホールで修学旅行の結団式を行いました。式では実行委員長の挨拶に始まり、教頭先生から東京に行った時の留意点などを含めた激励のお話をいただきました。修学旅行は5月16日(木)から18日(土)の日程となっていますが、いよいよ気持ちも高まってきたように感じます。
 「香味焼き」について
「香味焼き」について
今日の給食献立メニューは「ごはん・牛乳・あじの香味焼き・昆布のそぼろ煮・ピリ辛みそ汁」です。今日は「香味焼き」についてのお話です。今日の給食の「あじ」は「香味焼き」という調理方法で味付けされています。では「香味焼き」とは、いったいどんな調理方法なのでしょうか。「香味焼き」とは、季節の香物(しょうが、にんにく、ごまの香り高い野菜など)を使い香りを移しながら焼く調理方法で、四季を楽しむことが出来る料理なのです。「あじ」などの魚に特有の臭みを感じるため、残す生徒や嫌いになる生徒が多いのだそうです。そこで、給食センターでは、「香味焼き」などの調理法で臭みを少なくしたり、ごはんに合うような味付けにしたり工夫しているそうです。いつも生徒のことを考え、味付けやメニューを考えてくださり、本当に感謝しております。
 朝会を行いました
朝会を行いました
朝の時間に朝会を行いました。始めに賞状伝達を行い、野球部・バレーボール部・男子ソフトテニス部が表彰され、栄光を称えることができました。本当におめでとうございます。次に教育実習生の紹介を行いました。教育実習生は国語科で、今日から31日(金)までの15日間お世話になります。どうぞよろしくお願いいたします。最後に校長先生からお話をいただきました。「月曜日の朝からたくさんの賞状伝達ができたことを嬉しく思います。これも日頃から熱心に部活動に取り組んだ成果なので、来月の中総体も期待しています。」「“ローマは一日にして成らず”という、ことわざがあるように、部活動も勉強も、日々の積み重ねを大切にすることで、良い成績・良い結果に結び付くので、諦めないで努力し続けてほしい。」「教室前方に掲示してある、目指す生徒像をもう一度確認し、日々の心の持ち方を考え、それを行動に移していくなど、心の習慣を身に付けてほしい。」など、これからの西中生に期待する内容の話がありました。今週は修学旅行や仙台研修などの行事があります。体調管理にも気を付けて過ごしていきましょう。
 体育祭縦割集会を行いました
体育祭縦割集会を行いました
6校時に紅組青組に分かれて、体育祭縦割集会を行いました。各学年、体育祭応援リーダーから自己紹介と意気込みを堂々と発表することができました。また、団長からは、盛り上がる応援やエールを行い、どの生徒もとても楽しそうに活動していました。縦割での活動を通して、新しい出会いがあり、ひと回り大きく成長してくれることを願っています。
 「竹の子」について
「竹の子」について
今日の給食献立メニューは「ごはん・牛乳・牛タンつくねオニオンソース・チャプチェ・竹の子のスープ」です。今日は「竹の子」についてのお話です。「竹の子」は、春に旬を迎え独特の香りとシャキシャキとした食感が特徴的です。また、「竹の子」は、体を作る上で欠かすことのできない、たんぱく質やカリウム、食物繊維などを含んでいる、栄養面でも魅力がある野菜なのです。加えて、チロシンという聞きなじみのない栄養も含まれています。チロシンは、たんぱく質の元となるアミノ酸の一種であり、ドーパミンという神経伝達物質を合成する際に必要で、幸せを感じたり集中力を上げたりするなど、脳を活性化させる働きがあるそうです。竹の子を切ると、中心部分に白い粉のようなものがあり、それがチロシンです。竹の子からも幸せをたくさん感じることができた給食でした。
 1年生も授業でタブレットを使用できるようになりました
1年生も授業でタブレットを使用できるようになりました
先月1年生用のタブレットが学校に届き、全員が使用できる環境整備等の準備が整ったため、今週から1年生もタブレットを授業などで使用するようになりました。これからタブレットを効果的に活用することで、学習の幅が広がったり、より主体的に学習ができたり、学習のモチベーションが高まったりすることでしょう。
 「けんちん汁」について
「けんちん汁」について
今日の給食献立メニューは「ごはん・牛乳・カツオと大豆のゴマがらめ・ひじき和え・けんちん汁」です。今日は「けんちん汁」についてのお話です。「けんちん汁」とは、大根やにんじんなどの野菜を油で炒めてから煮込む料理のことで、その発祥には諸説あり、鎌倉の建長寺で作られる「建長汁」という名前が「けんちん汁」と呼ばれるようになったという説があるそうです。「けんちん汁」は、建長寺で700年以上も前から食されており、一説によると、建長寺で修業した僧侶が各地に派遣されるとともに全国に広まっていったと言われています。また、建長寺の「けんちん汁」は精進料理であるため、動物性の食品は使わず、だしも昆布やしいたけからとります。粗食のイメージがある精進料理ですが、多くの野菜が使われているため、だしのきいた、風味豊かな味わいです。様々な食材の風味を楽しみながら、美味しくいただくことができました。
 中央委員会を行いました
中央委員会を行いました
放課後の時間に中央委員会を行いました。今回は生徒総会に向けた準備がメインになりました。例年通りの内容もありましたが、新しい意見もあり、日々挑戦し続ける西中に感心しました。生徒も真剣に相談したり調べたり考えたりと充実した委員会になっていたように思います。
 「小魚」について
「小魚」について
今日の給食献立メニューは「チーズパン・牛乳・ツナオムレツ・キャベツとコーンのソテー・クラムチャウダー・小魚」です。今日は「小魚」についてのお話です。給食の「小魚」は、乾燥小魚で、カタクチイワシを使用しています。頭からしっぽまで丸ごと食べられるので、カルシウムを多くとることができます。カルシウムには、骨や歯を作るほか、イライラを防いだり、心臓の働きを正常に保ったりする働きがあります。また、小魚のカルシウム吸収率は約33%で、牛乳の約40%に比べると少し低めですが、小魚には血液を作る鉄分、目の疲れをとるビタミンAなども多く含まれています。小さな魚なのにたくさんの栄養素があることに驚きました。
 歯科検診を行いました
歯科検診を行いました
午前中に全校生徒を対象に歯科検診を行いました。静かに順番を待つ生徒はむし歯等がないか心配している様子でした。今回の検査結果をもとに、毎日の歯磨きの見直しを声掛けしていきたいと思います。
 「みしょうかん」について
「みしょうかん」について
今日の給食献立メニューは「ごはん・牛乳・炒めビビンバ・中華風スープ・みしょうかん」です。今日は「みしょうかん」についてのお話です。「みしょうかん」は、ミカン科ミカン属ブンタン類の柑橘類の一種で、「河内晩柑(かわちばんかん)」という別名がある柑橘だそうです。また、「河内晩柑」という名前は、発見された地名の「河内」と、収穫時期の遅い「晩成の柑橘類」という意味で名付けられたと言われています。「みしょうかん」は、さわやかな香りと、ジューシーで上品な甘酸っぱさがある味わいが特徴です。グレープフルーツとよく似た見た目をしていますが、グレープフルーツと比べると苦味や酸味が少ないので、生徒も美味しそうに食べることができました。今日もごちそうさまでした。
 ミニ大根づくりの作業を頑張りました
ミニ大根づくりの作業を頑張りました
1年生は技術の授業で、「ミニ大根づくりを成功させよ」という課題で、ミニ大根づくりの作業に取り組みました。今日は最初の授業ということで、プランターに培養土と有機肥料を入れ、種まきを行いました。指を使ったまき方「点まき」を丁寧に行う様子が見られました。また、友達と協力しながら、楽しそうに活動していました。これから、水やりなどのお世話をして、ミニ大根づくりを大成功させてほしいです。連休明けの授業でしたが、元気に過ごしていて安心しました。明日からも、様々な活動に一生懸命取り組むことが楽しみです。
 石巻地区中学校ソフトテニス春季大会が行われました
石巻地区中学校ソフトテニス春季大会が行われました
5月3日(金)に追波川河川運動公園テニスコートで、石巻地区中学校ソフトテニス春季大会が開催されました。普段より気温は高かったのですが、絶好のテニス日和の中、一日目の団体戦が行われました。生徒は朝から緊張ムードでウォーミングアップから思うようにプレーができず、あまり体も動いていないように見えました。そこで、団体戦の試合の前には全員で円陣を組み、「ミスを恐れず全力でプレーしよう」「最後まで諦めずにボール食らい付き粘り強く戦おう」「何より楽しく笑顔を忘れないこと」「全員で勝利を掴み取ろう」などを選手と監督で確認し試合に挑みました。苦戦しながらも何とか勝ち進み、遂に因縁のライバルとの戦いになりました。これを勝てば3位ということで、より張り詰めた緊張感の中、試合が始まりました。試合はどちらも一歩も譲らず、ファイナルゲームまで縺れる試合展開でした。とても白熱した試合に応援もヒートアップし、声がかれるまで必死になって応援しました。何度もマッチポイントを取られ落ち込みそうでしたが、ここで、西中の頼れる大黒柱がやってくれました。険悪な雰囲気をものともせず、元気な声で自分を鼓舞し、勝利のために諦めずに戦い抜きました。そして遂に勝利を掴み取ることができました!喜びの声と嬉しい表情、涙で選手も応援も大興奮でした。その後の準決勝は、勢いそのままに、善戦しましたが、惜しくも惜敗し団体3位という結果に終わりました。しかし、生徒は満足感でいっぱいです。今回の団体戦を通して「自分たちがここまで戦えること」「全員で勝利を掴み取れたこと」「持てる力を存分に発揮できたこと」などを感じていて、中総体につながる価値のある大会になりました。男子ソフトテニス部の皆さん。本当によく頑張りました。まずは、ゆっくり休んで、中総体に向けてラストスパート頑張りましょう!
 避難訓練・引き渡し訓練を実施しました
避難訓練・引き渡し訓練を実施しました
6時間目に避難訓練・引き渡し訓練を実施しました。今回の訓練は、大きな地震がきたことを想定して行いました。生徒は机を利用し頭を守ったり、できるだけ窓際から離れ自身の身を守ったりしていました。その後、学級担任の指示のもと、校庭に避難しました。生徒は素早く非難し、教員の指示をしっかりと聞き落ち着いて行動できていました。避難訓練に続いて引き渡し訓練を行いました。西中ホールで一人一人名簿を確認しながら迎えにきた家族の方に引き渡しました。安全に引き渡すことができたことや生徒が最後まで真剣に取り組めたこと、更には、多くの保護者やご家族の皆様が引き渡し訓練に参加していただいたことを大変嬉しく感じます。また、学校運営協議会の方々にもご協力をいただき、誠にありがとうございました。
 「こどもの日」について
「こどもの日」について
今日の給食は「こどもの日」献立ということで、メニューは「タケノコごはん・牛乳・こどもの日ハンバーグ・もやしのツナ炒め・めかぶのスープ・こいのぼりボーロ」です。今日は「こどもの日」についてのお話です。もともと5月5日は「端午の節句」で、男の子の健やかな成長や幸せを祈ってお祝いをする日でした。1948年に、5月5日を「こどもの人格を重んじ、こどもの幸福をはかるとともに、母に感謝する」お休みの日と決められてから、端午の節句の日が、「こどもの日」にもなったそうです。そのため今では、子どもたちみんなをお祝いするようになりました。子どものお祝いだけじゃなくて「お母さんに感謝する」という意味もあったのです。そんな「こどもの日」に因んで、今日の給食は人気メニューである「タケノコごはん・ハンバーグ」が出ています。そのため生徒はとても喜んで食べている様子でした。満足そうな生徒の表情を見て先生方も嬉しくなりました。とても大満足でした。ごちそうさまでした。
 専門委員会を行いました
専門委員会を行いました
放課後に専門委員会を行いました。今回の内容としては、4月の活動の反省と5月の活動内容の確認、目標設定などでした。また、5月に行われる生徒総会に向けての資料準備も行いました。期間の短い中でも計画的に準備を進める西中生に感心しました。全体として4月の委員会活動では、1年生は不慣れながらも、友達と協力しながら、先輩に助けられながら、一生懸命取り組んでいるようでした。4月の反省を活かしながら、5月は1年生だけでも活動できるように、期待しています。
 解団式を行いました
解団式を行いました
1年生は解団式を行いました。校長先生からは「この松島研修で学んだことや楽しかったことを、自分の経験値として今後に役立ててほしい」「この1年生のメンバーの誰とでも仲良く付き合いながら、中学校生活を送ってほしい」などの話がありました。代表生徒の感想発表では「友達と協力しながら活動できてよかったし、多くの人と交流できて嬉しかったです」「どの活動も初めてで、すべていい思い出になりました」などと、喜びを感じながら話をしていました。改めて松島研修が大成功だったと感じています。
 「南部揚げ」について
「南部揚げ」について
今日の給食献立メニューは「豆乳食パン・牛乳・笹かまの南部揚げ・刻み昆布サラダ・山菜うどん・シャーベットヨーグルト」です。今日は「南部揚げ」についてのお話です。今日の給食の「笹かまの南部揚げ」の「南部揚げ」とは何のことでしょう。「南部揚げ」とは、変わり揚げの一種であり、材料には小麦粉、卵白、ごまなどを順につけて揚げたもののことをいうそうです。南部地方(現在の岩手県と青森県にまたがる地方)が、ごまの名産地であることから、ごまを用いた料理を「南部○○」という呼び名が付けられているとのことです。今日の給食は、ごまの香りを楽しみながら美味しくいただくことができました。
 部活動ミーティングを行いました
部活動ミーティングを行いました
放課後に、新たに入部した1年生も参加して部活動ミーティングを行いました。どの部も楽しい雰囲気の中、自己紹介や目標の確認、今後の予定の確認など、充実したミーティングを行っていたように思います。2・3年生の皆さん、まだまだ分からないことの多い1年生ですが、丁寧かつ優しく教えてあげるようお願いします。
 野球部が「石巻かほく杯中学校野球大会」で優勝しました(5年ぶり3回目)
野球部が「石巻かほく杯中学校野球大会」で優勝しました(5年ぶり3回目)
4月27日と28日に行われた「石巻かほく杯中学校野球大会(三陸河北新報社・河北新報社主催)」で、本校野球部が5年ぶり3回目となる優勝の栄冠を勝ち取りました。決勝戦では宿敵ともいえる石巻中学校チームと対戦しました。1回に2点を先行されたものの3回に同点に追いつき、その後シーソーゲームとなりましたが、同点で迎えた最終回に2点を取り、そのまま相手の攻撃を制して勝つことができました。粘り強く戦う姿勢と精神力が見事で、昨年の新人大会と同県大会での激闘の経験が生きていると感じました。また、大会での活躍が認められ、主将(捕手)の生徒が最優秀選手に、投手・遊撃手の生徒が優秀選手に選出されました。おめでとうございました。なお、今日は放課後に部員の皆さんが校長室に優勝の報告に来てくれました。
 「玄米入りご飯」について
「玄米入りご飯」について
今日の給食献立メニューは「玄米入りごはん・牛乳・いわしの梅煮・ひじき炒め・じゃがいものみそ汁・いちごミルクプリン」です。今日は「玄米入りご飯」についてのお話です。今日の玄米入りご飯の「玄米」は「金のいぶき」という宮城県産の米を使っています。2011年の春、東日本大震災直後、田んぼに植えられ、たくましく生き抜いたお米は、宮城の希望となり、一粒一粒の輝きから「金のいぶき」と名付けられたそうです。胚芽が通常の玄米の3倍もの大きさになるため、ビタミンB群やビタミンEがたくさん含まれています。地元の食材を美味しく食べられることにとても感謝しています。また、今日の給食の「いちごミルクプリン」は大好評でした!
 朝会を行いました
朝会を行いました
3連休明けではありましたが、始業前から元気のよい生徒の声が響き渡っていました。そんな中、朝の時間に朝会を行いました。校長先生のお話は「認知特性」についてでした。「認知特性は大きく分けると視覚優位者・言語優位者・聴覚優位者の3つに分類され、さらにそれぞれが2つに分けられると言われている」ことに触れ、それぞれの特性ごとの特徴やその特徴に応じた勉強方法などを分かりやすくスライドにまとめて紹介していました。また、「自分でセルフチェックを行い、自分の認知特性を知って、それを参考にすることでより自分に合った勉強方法を工夫してみてはどうか」「認知特性に優劣はないことなどの認知特性の理解についての留意事項など」のお話もありました。生徒は早速、認知特性について興味を示し、休み時間にセルフチェックをしているようでした。生徒にとっては、とても関心の高い内容だったように思います。

 松島宿泊研修に行ってきました
松島宿泊研修に行ってきました
4月25日(木)、26日(金)に1年生は松島宿泊研修に行ってきました。2日間、天候にも恵まれ、すべての体験プログラムを終えることができました。研修からたくさんの思い出をつくることができ、交友関係も深めることができました。また、様々な体験活動を通して、自主性・協調性・計画性などを養ったり、達成感・成就感を体感したりと、多くのことを学ぶことができました。これは今後の学校生活や将来にもつながるもので、非常に価値ある経験になりました。研修中、生徒はとても立派で、教員も一緒に楽しいひと時を過ごすことができました。大成功だった松島宿泊研修、今後の1学年の成長が楽しみになりました。
1年生の皆さん。しっかりと体を休めて、来週からも元気に活動しましょう!
※以下、活動の様子を一部紹介します。
<出発、バスでの様子>
【1日目】
<入所式、オリエンテーションの様子>
<宮戸島ウォークラリーの様子>
<海岸での海遊びの様子>
<昼食の様子>
<MAP(みやぎアドベンチャープログラム)の様子>
<ロープワークの様子>
<夕べのつどいの様子>
<夕食の様子>
<部屋での様子>
<レクレーション(ドッチビー・ドッチボール)の様子>
【2日目】
<朝のつどいの様子>
<朝食の様子>
<防災体験プログラムの様子>
<野外炊飯(ふわふわピザ)の様子>
<自由時間の様子>
<退所式の様子>
簡単ではありますが、以上で紹介を終わります。最後までご覧いただき、誠にありがとうございました。_(._.)_ペコリ
 掲示物「数学日和」「数学道場」の紹介です
掲示物「数学日和」「数学道場」の紹介です
1年生と3年生の教室前廊下に、数学の先生が運用している「数学日和」と「数学道場」という掲示物があります。「数学日和」は1年生向けの内容で、授業では扱わないような小学校の算数の難問を出題しています。また、「数学道場」では、発展問題や入試問題などを出題しています。勉強や学習は授業時間だけで完結するものではなく、学力や学習力を高めていくには家庭学習を含め、授業時間以外の時間の勉強や学習が必要不可欠です。学びの出発点は「知的な好奇心」にあるといわれますので、数学に対する興味・関心が少しでも高まるといいなと思います。
 1年生の松島宿泊研修が始まりました
1年生の松島宿泊研修が始まりました
今日と明日は1年生の松島宿泊研修です。8時から西中ホールで出発式を行ったあと、生徒の皆さんは学級ごとにバスに乗車し、松島自然の家に向けて学校を後にしました。一晩降り続いた雨も出発時には上がり、青空が広がりましたので、きっとすがすがしい気持ちで出発できたのではないかと思います。
 いよいよ明日から松島宿泊研修!
いよいよ明日から松島宿泊研修!
松島宿泊研修を明日に控えた1年生は、本日6校時に結団式を行いました。「We are one」というスローガンのもと宿泊研修をし、「集団生活、集団行動を通してお互いに理解と友情を深めること」や「体験活動を通して、自主性・協調性・計画性を養うこと」などの目的を達成してくることを再確認しました。何より安全第一で体調管理にも留意しながら楽しく過ごしてきたいと思います。
※宿泊研修の様子は後日アップします。楽しみにお待ちください。_(._.)_
 心臓病検診を行いました
心臓病検診を行いました
5校時目に1年生を対象とした心臓病検診を実施しました。生徒は緊張した面持ちでしたが、検査を終えた生徒には笑顔があり、談笑する様子も見られたので安心しました。
 「ミネストローネ」について
「ミネストローネ」について
今日の給食献立メニューは「ミルクパン・牛乳・ハムチーズピカタ・ペンネソテー・ミネストローネ・アセロラゼリー」です。今日は「ミネストローネ」についてのお話です。「ミネストローネ」はイタリア料理の一つで、トマトやジャガイモ、ニンジンや玉ねぎなどの野菜を煮込んだスープです。野菜などを具沢山に入れたスープのことを、「ミネストローネ」といい、イタリアでは古くから家庭料理として食べられてきたそうです。また、使われる食材は、地域や家庭、季節によって違ってきますが、セロリやキャベツ、ズッキーニなどの野菜、ベーコンやパスタ、米などをいれる場合もあるそうです。様々な食材を煮込んで作っているため、栄養満点のスープになっています。美味しく味わいながら、しっかりと栄養補給をすることができました。今日もごちそうさまでした。
 市学力調査を行いました
市学力調査を行いました
3・4校時目に全学年の生徒を対象とした学力調査を実施しました。国語と数学の2教科の試験を受けました。一生懸命に考えようとする姿や、最後まで諦めずに取り組む様子、時間ギリギリまで見直しをする姿勢にはとても感心しました。さすが西中生です。結果を楽しみに待ちたいと思います。
 松島宿泊研修に向けて準備が進んでいます
松島宿泊研修に向けて準備が進んでいます
1年生は今週の木・金曜日に予定されている松島宿泊研修に向けて、今日、しおりの製本や読み合わせ、係決めなどを行いました。活動する生徒の様子をみると、ワクワクから楽しみにしている生徒がほとんどだと見て取れました。しっかりと宿泊研修の目的と目標を再確認し、実りある充実した研修になるようしたいと思います。これから生徒の体調管理も含め、最後まで事前準備を行っていきます。
 「タンドリーチキン」について
「タンドリーチキン」について
今日の給食献立メニューは「ごはん・牛乳・タンドリーチキン・チーズ入りポパイサラダ・キャベツのスープ」です。今日は「タンドリーチキン」についてのお話です。「タンドリーチキン」とは、インド料理の一つで、様々なスパイスとヨーグルトを合わせタレに漬けこんで、カレー風味に味付けをして衣をつけて油で揚げて作ります。カレーの鮮やかな色合いと香ばしい香りが食欲をそそるのが特徴です。ジューシーで風味豊かな味わいに生徒はとても喜んでいるようでした。満足そうな表情を浮かべながら今日もごちそうさまでした。
 避難訓練を行いました
避難訓練を行いました
6校時目に避難訓練を実施しました。今回は火災が発生したことを想定して行いました。学年ごと決められた避難経路通りに避難し、校庭に素早く集まることができました。避難する生徒には、ハンカチで口を覆ったり、お互いに確認し合いながら行動したりと、大変立派に訓練を行うことができました。また、火災の際の初期消火の訓練も実施しました。各学年の代表が練習用の消火器を使い初期消火を行いました。大きな声で周囲に家事を知らせたり、手早く消火器を準備したり感心しました。代表の生徒に感想を聞くと、「緊張したけど、スムーズに消火できてよかったです。とても貴重な経験ができました。」などの感想を話していました。今後も、「いつ・どこで・どんな」災害が起こるか分からないことを頭に入れて生活をするよう、声掛けしていきたいと思います。
 「すまし汁」について
「すまし汁」について
今日の給食献立メニューは「ごはん・牛乳・サバのごまみそ焼き・五目きんぴら・豆腐団子と油麩のすまし汁」です。今日は「すまし汁」についてのお話です。「すまし汁」は漢字で「澄まし汁」と書きます。漢字の通り“澄んだだし汁”がメインの料理になります。日本の伝統料理に「お吸い物」があります。「お吸い物」とは、かつお節や昆布などでとっただし汁に塩や醤油で味付けされ、具材には肉や魚介類、野菜が入ったもののことを言います。「お吸い物」は、「すまし汁」と混同されてしまいますが、「お吸い物」は“汁と具材”がメインになります。いつも大変勉強になります。
 1年生、入学してから早2週間
1年生、入学してから早2週間
時の流れは早いもので、1年生が入学してから2週間が経過しました。とても元気のよい1年生で、何の活動をするにしても前向きで、熱心に取り組む姿がたくさん見られます。また、友人関係の仲がとてもよく、休み時間の度に学級関係なく交流し、笑い声が響き渡るほど、いい雰囲気で生活しています。お陰様で先生方もとても気持ちよく、楽しく学校生活を送ることができています。そろそろ疲れも見られる頃だと思うので、生徒の体調面を気にしながら声掛け等を行っていき、来週に控えた松島宿泊研修に備えたいと思います。
1年生の皆さん。週末は疲れた体を癒して、来週も元気に頑張りましょう!
 PTA総会・学年PTAを行いました
PTA総会・学年PTAを行いました
5校時の学習参観終了後、PTA総会・学年PTAを行いました。多くの皆様にご参加いただき有意義な会となりました。誠にありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。
 学習参観を行いました
学習参観を行いました
5時間目に今年度1回目の学習参観を行いました。多くの保護者の皆様にご来校いただきまして誠にありがとうございました。
 「食育の日」について
「食育の日」について
今日の給食献立メニューは「わかめごはん・牛乳・笹かまのごまフライ・チョレギサラダ・塩ワンタンスープ」です。今日は「食育の日」についてのお話です。毎月19日は「食育の日」と呼ばれ、地場産品や郷土料理をたくさん取り入れる給食になっています。今日の「笹かまぼこ」は石巻市内の工場で作っていて、給食を提供する時間に合わせて作業を進めているそうです。この「笹かまぼこ」には、ごまやチーズが入っていて、たくさん栄養価が詰まった一品となっています。給食センターの方々は、子供の成長のことを考えたメニューにしているので、毎日、感謝の気持ちを持つよう、生徒にはお話ししていこうと思います。
 朝のあいさつ運動を行っています
朝のあいさつ運動を行っています
月曜日と金曜日の朝には、生徒会執行部と生活委員の面々が昇降口前に立って、朝のあいさつ運動を行っています。今日も元気にあいさつを行っていました。
 学びの金言コーナーにメッセージが掲示されました
学びの金言コーナーにメッセージが掲示されました
今年度も生徒が将来、心豊かな生活を送るために今行うべき学びについて、先生方一人一人が思いを込めた熱いメッセージを掲示しています。早速掲示が始まりましたので紹介します。
<校長先生からのメッセージ>
「めざせ記憶上手!」です。校長先生曰く『先日の朝会でお話したことを受けて、今回はこの言葉を改めて送ります。知識は覚えて使うからこそ価値をもつものです。これからは「AIが発達するし、人間の記憶はコンピュータには到底かなわない、だから必要なのは暗記よりも考える力をつけることだ!」などという人もいますが、自分で考えたり、判断したりするためには、その土台や基準となる知識をもっていることが必要です。そもそも、ものごとを知らない人が、深く思考したり、適切に判断したりできるのか、と考えたときに、「まずは理解し、理解できたことを覚えていて、それを使う事ができるようにしようとする行為」こそが”勉強”の意味なのではないかと思うわけです。知識のない人に論理的な思考力を求めても難しいものですし、情緒的・感覚的に判断し行動することは人間以外の動物でも行っていることです。複雑化した現代を生きる人間がより人間らしく生きていくためには勉強してたくさん学ぶことが大切なのではないでしょうか。西中の生徒の皆さんには、どんどん知的好奇心を高め、知識を理解して身に付け、豊かな人生を送ってほしいのです。』とのことでした。
<国語科のI先生からのメッセージ>
「実践が実を結ぶ。経験が思考を高める。経験を積んできた、父、母、兄、姉、祖父母の言葉に、君たちが成長するヒントがある。失敗談も参考になるぞ。耳を傾けよ!」です。I先生曰く「今までの先人たちはこれからの生徒のみなさんに役立つために学び・経験し伝えている。その知恵を受け取り自分に活かそう。過去から学ぼう。先人の知恵を役立てよう。先人から学ぶことを始めて、先人の知恵を役立てよう。」とのことでした。
熱い思いが生徒に伝わり、より一層、励むことを期待しています。
 昇降口に各学年の目標が掲示されました
昇降口に各学年の目標が掲示されました
昇降口の入り口上部に各学年の先生方が考えた、生徒に意識してほしいことを「○○月間」として掲示しています。今年度も4・5月の目標が掲示されましたので紹介します。
〇1年生「西中に慣れよう月間」
〇2年生「アウトプット強化月間」
〇3年生「自分を知ろう!自己探求月間」
大きく羽ばたけ西中生!
 1年生の部活動見学・体験の様子
1年生の部活動見学・体験の様子
1年生は正式入部になるまで、放課後の時間に好きな部活動を見学・体験する時間になります。すでに入る部が決まっていて、早速、用具を持参して、先輩と一緒に部活動を行っている生徒もいて、意欲の高さを感じました。また、まだ決まっていない生徒も先輩方が優しく丁寧に接してくれたおかげで、とても楽しそうに活動している様子が見られました。そのため、どの部もいい雰囲気の中で活動していて感心しました。
 校庭の草刈作業を行っています
校庭の草刈作業を行っています
今日は用務員さんが校庭の草刈作業を行っていました。乗用タイプの草刈機ではありますが、なにぶん校庭が広いため、相当に時間がかかる作業なのです。春になりせっかく張り切って背を伸ばしてきた草にとっては大きな災難ではありますが、やむなしといったところです。
 「いちご」について
「いちご」について
今日の給食献立メニューは「ごはん・牛乳・ポークカレー・もやしのツナ炒め・いちご」です。今日は「いちご」についてのお話です。今日の「いちご」は石巻で栽培していて、この時期の「いちご」は少し、酸味があるそうです。「いちご」の表面にある「つぶつぶ」は、種ではなく、一つ一つが果実なのです。「つぶつぶ」の中に種が入っていて、一粒に200~300個の果実が集まった集合果と言われているそうです。そのため、ビタミンCが豊富なので、血管や皮膚づくりに働くそうです。果実って不思議だなと思いました。また、今日の給食のポークカレーは生徒の大人気メニューだったので、喜んで食べている様子が見られました。今日も美味しく完食です!ごちそうさまでした!
 全国学力・学習状況調査が行われました
全国学力・学習状況調査が行われました
本日、3年生は全国学力・学習状況調査を受けました。今年度は国語と数学の2教科が対象です。この学力調査は、生徒一人一人の学力や学習状況を把握・分析することにより、国や地方公共団体が教育施策の成果と課題を検証し改善を図ることや、各学校が今後の教育指導や学習状況の改善等に役立てることを目的として実施しています。受けた西中生は熱心に問題に取り組んでいる様子でした。この調査結果を分析し、今後に活かしていきたいと思います。
 2年生の朝活動の様子の紹介です
2年生の朝活動の様子の紹介です
今日の2年生の朝活動は「100マス計算」でした。「始め」の合図で計算に取り掛かりますが、「カリカリ」と書く音が響き、よく集中して熱心に課題に取り組んでいる姿は、とても素晴らしいと感じます。こういう取組も「みんなで学ぶ」という学校のよさが感じられる場面です。
「100マス計算」というと小学校の算数の正の数の加減乗除の計算のイメージですが、本校の100マス計算は中学生の学習に合わせて「正負の数の計算」や「文字式の計算」などを問題としています。今日は一桁の正負の整数の足し算の問題でした。「速さ」と「正確さ」の両方を高めながら基礎的な計算力をつけることは、そのあとの学習である方程式や関数などの問題を解く力も向上していくことにつながるのです。”計算力が弱いのに数学が得意”な人はいないものです。同じように”英単語をあまり覚えていないのに英語が得意”な人もいないものです。
 いわゆる”置き勉”について
いわゆる”置き勉”について
本校では登下校時の荷物を減らし軽量化を図るために授業の用意を学校においておく、いわゆる”置き勉”を教科により認めています。教室のロッカーは通学用カバンだけでいっぱいなので、今年は個人用のケースを用意し、各学年の学年室にまとめておいておくようにしました。これは誰も他の人のものを持ち去ったり、いたずらしたりすることがないために、いわば治安がよいことで実現できていることです。このようにみんながルールやマナーを守って安心して生活できることは、当たり前のようでなかなかそうでもないことなのです。
 「石巻焼きそば」について
「石巻焼きそば」について
今日の給食献立メニューは「背割りソフトパン・牛乳・のり塩コロッケ・焼きそば・フルーツヨーグルト和え」です。今日は「石巻焼きそば」についてのお話です。石巻の学校給食の焼きそばには石巻焼きそばの麺が使われています。石巻焼きそばの特徴としては、二度蒸しているので、茶色です。また、かつおやサバなど4種類の出汁で蒸し焼きにした出汁風味の焼きそばになっています。地元グルメだけに生徒の大人気メニューのため、大盛りにする生徒やおかわりをする生徒が多かったです。さらに、1年生は焼きそば完食です!素晴らしい!皆さんたくさん食べました。ごちそうさまでした。
 草木の命の鼓動を感じるこの頃です
草木の命の鼓動を感じるこの頃です
満開だった桜も今日は随分と散ってしまい、代わって一冬を耐えた木々には新しい葉が出てきました。花壇の花も元気いっぱいに咲き誇こり、校庭の草も伸びてたくさんの黄色い花が咲いています。(用務員さんは草刈りが大変だなぁと嘆いていましたが…。)草木の力強さを感じる成長の様子とすがすがしい天候とが相まって、自然にやる気が湧いてくるかのようです。
【WEB版なるほどコーナー】落葉樹が冬に葉を落とすのは冬をやり過ごすためだそうです。誰もが知っているように、葉は太陽の光を受けて光合成により栄養を作り出すための器官です。冬の間は日照時間が短く、葉を付けていても十分に太陽光を得ることができないために多くの栄養を作れない一方で、葉を維持するために代謝は行わなければならず、さらに雪が降ると葉の上に積もった雪の重みで枝が折れやすくなってしまいます。そのため、落葉する植物は冬の間は、栄養を生産することを諦め、春に向けてできるだけ傷を作らないようにしてひっそりとやり過ごそうとしているのだそうです。自然というのは不思議なものですし、よくできています。